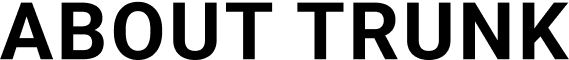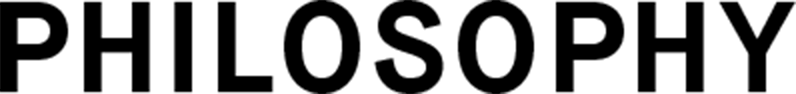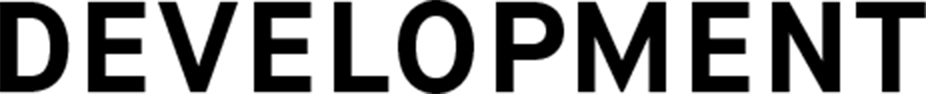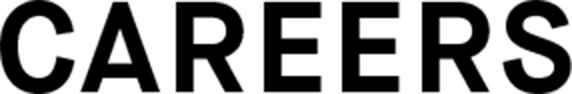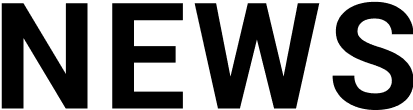TRUNK社長 野尻佳孝による、多様な業態が凝縮した「ホテル」という存在について語り尽くす企画。今回は、TRUNKが何よりも重要視するクリエイティビティについての考察と実践についてお伝えします。
なぜクリエイティビティが大切なのか。
旅の経験値が高く、世界中の面白い場所へ行きたい、面白い人たちと会いたいという感度の高い人々。TRUNK(HOTEL)がターゲットとしているお客様は、そんな人たちなんです。感度の高いお客様にご満足頂くためには、やはりクリエイティビティを高めていくことが何よりも大切なことだと考えています。

創造性を担う、「アトリエ」という部署。
一般的には設計会社等に外注する仕事も、TRUNKでは内製化しています。例えば、空間をどう設計していくかというゾーニングを企てる人間だけでも4、5人を抱え、常日頃から新しい物件をイメージして、「こういう設計がいいんじゃないか」と議論しています。
一方でどんな飲食店がいいのか、どんなコンセプトのレストランが必要なのか、フード&ビバレッジ等のコンテンツを企画開発するディレクターは兼任を含めると5人もいる。部屋の構成、水回りを考える専任者がいたり、制服やアメニティのようなプロダクトを企画、制作するディレクターが2、3人。イベントやパーティーの企画プロデューサーもいれば、グラフィックデザイナー、フォトグラファーや映像クリエイターまでも内製化しています。そういったクリエイティブを考えるチームを「アトリエ」と呼んでいますが、そういう人材だけで20名以上が社内で働いているんです。

アトリエメンバー
効率化よりも創造性を。
社内に前述のような機能を抱えているホテルは、日本では他にないと思います。世界中のホテリエたちと会っても、クリエイティブ全般を網羅するチームを抱えるホテルはほとんどないですね。しかも、1つのホテルしかないのに、アトリエのメンバーが20名以上もいる会社なんてないと思うんです(笑)。でも、アパレルのような業態は、この「アトリエ」の機能が生命線ですよね。私はホテルも同じ、クリエイティブな仕事をしていると思っています。そういう人間が専任として社内にいないと、良いものを生み出せない。
仮に偶発的に生み出すことができたとしても、維持向上することが難しくなります。もちろんコストはかかります。でも、そういう意味でも振り切っていく。そこに私たちのクリエイティブに対する覚悟のようなものがあるというか。コストをかけてもクリエイティブを第一に考えるんだという意識ですよね。本当に良いものをつくれば、興味を持ってくれる人は世界中にいるという強い信念がありますから。
TRUNKで働くすべての人々に求められるもの。

効率化やコストカットとは真逆の発想で、非効率を重んじて手間暇をかけてこだわっていく。建築やデザインという意味でももちろんそうですが、「アトリエ」だけがクリエイティブを担っていてもダメなんです。
「アトリエ」がコンセプトをつくって、商品をつくって、あとは運営チームに頼むぞって渡しても、そこにギャップがあっては意味がないと思っています。お客様と向き合う運営メンバーにも、高いクリエイティビティが必要です。そのために、TRUNKにはマニュアルがありません。マニュアルをつくってしまうと、思考が止まって想像力が働かないのです。
どうしたらいいのか、日々お客様と向き合いながら自問自答する必要がある。会社がこういうものを学びなさいと指示しても意味がありません。なぜならホテルは多種多様な人々が集う場所だから。朝早く起きてコーヒーを飲みながらリラックスしに来てくれる人もいれば、休みの日に家族みんなで食事に来ることもある。昼間に仕事のミーティングで使う人もいれば、仕事終わりで遊びに来る人もいる。そのすべての人にマニュアルで対応することなんてできないと考えます。
自発的にクリエイティビティを高めるための体制づくり。
だから、本人がいかに自発的に動くことができるようにするのか、環境を設計することが必要です。自分の意志で、クリエイティビティを高めるために動ける体制づくりが大切だと思っています。

有志が集まり人事制度を考える、「みんプロ」
例えば、有志が集まって人事制度をつくって、いつ休むか、どんな働きかたがいいのか、自分たちで決定していることもひとつ。他にも自分が受けたい研修をカスタムメイドすることもできる。当然ホテル好きが多いので、自らの希望でブティックホテルを泊まり歩いたスタッフもいます。ビジネスにおけるコミュニケーションスキルを学びに行ったり、スポーツインストラクターの免許や国家資格を取得するための試験を受けに行ったり。それぞれのメンバーが、自分たちこそがTRUNK(HOTEL)の商品であることを理解してくれているんです。
スタッフに常に求められているのは、クリエイティビティを高める言動が取れているかどうか。クリエイティビティこそが、唯一、我々のアイデンティティと呼べるものかもしれない。